Dさんのお父さま
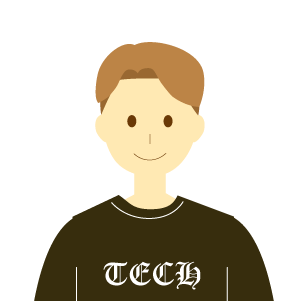
首都圏の過熱した中学受験には否定的だったため、当初は息子に中学受験をさせる気はあまり無く、公立中高一貫校の受験を検討する程度でした。
一方で息子本人は算数やパズルが大好きで、小学4年生の春頃には「なぞペー」や「ちゃれペー」をあらかたやり尽くしてしまい、新しい問題集を探すことに苦労していました。そんなとき、3年生向けのThink!Think!シグマを見つけ、息子は大いに楽しみながら通うようになりました。
ところが4年生になるとこのコースは設定されておらず、退塾も検討しました。しかし日曜探求に魅かれてシグマTECHに興味を持ち、週2回の通塾で夕食も家でとれるなら許容範囲かと悩んだ末、息子に提案し、入塾テストを受けることを決めました。
4年生の頃は、カルタ大会などゲーム的な要素を取り入れた授業も多く、楽しく通えると感じていました。高学年になると課題も増え、どうなるだろうかと様子を見守っていましたが、課題の多さを口にすることはあっても、それを辛いとか嫌だとは一度も言わず、いつも楽しそうに通っていました。
毎回、最寄り駅まで迎えに行き「今日はどうだった?」と尋ねると「楽しかった!」と目を輝かせながら即答する姿に、充実した学びができていると実感していました。
日々の通塾とは別に、シグマTECHに通って特に良かったと感じるものが、日曜探求とサマースクールでした。日曜探求の社会や理科の回で出かけたフィールドワークは、子どもにとって得難い学びの経験となり、複数の分野や単元が繋がっていることを実感できる機会になったようです。また、親子の良い思い出にもなりました。
特に国分寺を巡った回や、水族館の回の解散後に浜辺を子ども達が散策していた様子は印象深く残っています。
サマースクールも、親は同伴しませんでしたが、写真や本人の話から判断する限りとても楽しめたようでした。都会で育つ子どもにとって、自然体験ができる貴重な機会となり、自然の中で思いっきり遊ぶことで一段とたくましく成長する姿が見られました。こうした体験学習が、教室での学びを立体的に深めていったように思います。
重視していたのは、ゴール設定を「大学卒業後に本人が望む人生を送れるような種を蒔くこと」とし、中学受験はその過程に過ぎないという認識を忘れないことでした。
模擬試験の結果はどうしても気になってしまいますが、成長のタイミングは体格同様に個人差が大きいものでしょうから、常に“あと伸び重視”の姿勢を心に留めるよう努めていました。
そして何よりも、学問を楽しいと感じる心を大切にしたいと考え、模試などに送り出す時には「面白い問題が出るといいね」、帰り道では「面白い・学べる問題あった?」といった声掛けを心がけていました。
また、学習の内容やペースは本人とTECHに任せ、課題の進捗状況や授業の理解度などには口出ししないようにしていました。時々食卓で「最近はどんな単元をやっているの?」と話題にし、好奇心を広げるきっかけ程度にとどめていました。
子どもの学習面はTECHに全て外注したつもりで、親子の間では生活面での「育て」に注力し、役割を切り分けるよう意識していました。これは、親よりも外部の専門家の方が学習指導に適していると考えたためです。
息子は精神的な幼さからか、忘れっぽく目の前のことに意識を奪われやすい性質がありました。ですが幼稚園の園長先生の「教育は、ねじ込むのではなく擦り込むのです」という言葉を思い出しながら、軽めの調子で声掛けするよう心がけていました。
受験を通して、親の役割はマインドセットに関わることであり、具体的な行動を強いるものではないと再確認しました。声かけの内容もネガティブ・インセンティブではなく、ポジティブ・インセンティブを意識していました。この姿勢は、特に直前期の息子の安定感などに効果があったと感じています。
息子の将来に多様な選択肢が広がる学校が良いと考え、国際的な学びや探究的プログラムが充実した学校を中心に探していました。
しかし私自身は土地勘がなく、学校の特徴どころか名前も全く知らなかったため、興味を持った学校の説明会には複数回参加するようにしました。2月受験校については、どの学校も4〜5回は説明会(合同説明会も含めて)で話を聞きました
同じ質問を異なる先生に尋ねたり、答え難そうな質問や子育て相談のような質問もしてみました。そうすることで、オフィシャルな説明だけでは見えてこない学校の本音や素の部分が見えてくるように感じました。
最終的には、1人1人の先生が濁さず誤魔化さず自分の言葉で語ってくれる、と感じた学校を第1・第2志望にしました。特に武蔵は息子もとても気に入ったようで、親子共に感覚の合う学校に巡り会えたのだと思います。
志望校を検討する上で大学進学実績も参考にしましたが、大学の入学偏差値と社会での活躍が必ずしも一致しない例を多く知っていたので、あくまで参考程度にとどめました。ここでも、あと伸び重視の姿勢から、息子が6年間過ごすことで伸び伸びと学問を楽しみ、成長できるような環境(教育コンテンツ、施設、在校生の雰囲気等)を優先しました。
今となっては、各校の入試特徴にはそれなりに大きな違いがあり、必ずしも模試の偏差値にこだわる必要がないと思うのですが、その認識に至ったのは志望校を決めた後でした。
4年生の頃から息子の偏差値で可能性があり、興味のある学校を探していった結果、最終的には進学しても良いと思える学校の偏差値の幅が30近くになりました。これによりどれかには受かるだろう、受かったところに行けば良いのだと、気楽に構えることができたのは幸いでした。
2月入試の午前受験校への移動を考えると、朝のスケジュールを早める必要があることがわかったため、年明けから当日と同じ起床・朝食時間を習慣化しました。また、過去問演習のスケジュールは本人に任せ、相談された時のみ意見を述べ、回答用紙等の印刷のみを担当するようにしました。
小学校については、以前からつまらないと言って行きたがらなかったこともあり、2学期後半から休みがちになり、1月は始業式以外ほとんど登校しませんでした。
しかしこれも完全に本人の判断によるもので、学校に行くより過去問を解いている方が楽しいという理由からでした。一方で習い事のピアノと合気道には毎週欠かさず通っていました。受験前日の1月31日も道場に行き、本人も「本番前日に稽古できたのは良かった」と言っていました。
どうしても合否に意識が向き、不安になりがちな時期かと思いましたので、「入試というのは学校が準備する第0回目の授業のようなもので、しっかり問題用紙という授業を受け、思いっきり答案に自己紹介をして来よう」「合否は中学校の先生が判断することなので、こちらが気にしてもしょうがない、学校の先生がその学校に合う子を選ぶだけ。だから、自己紹介である答案には自分のできることや考え方を全部出し切って、先生が正しく判断できる材料にしよう」と伝えていました。
息子も過去問は解くよりも、テキストや参考書を見比べながら解説を読む方が学校の考えていることがわかって面白いと、学校との対話という感覚を楽しめていたようです。
受験テクニックに頼らず、最後まで本質的な学びを提供し続けてくださった先生方には感謝と敬意しかありません。国語が苦手だった息子は、6年生後半のオンライン個別指導でも国語を選択しました。最後まで思慮の浅いミスを繰り返したにもかかわらず、先生方は根気強く本質的な指導を続けてくださいました。
そして「ついに」というか「やっと」というか、2月入試が始まってから、これまで解けなかったような国語の問題が解けるようになり、息子自身も驚きながら入試会場を出てくるほど手応えを感じるに至りました。これは深い部分に本質的な思考力を育み続けていただいたからこそ、最後に様々な要素がつながったのだと思います。
振り返ると様々な学びや成長がありましたが、特に大きな転機となったのは4年生時のクラス替えだったように思います。当初、好きな算数ばかりに取り組み、他の科目を疎かにする傾向が強く、バランスの悪さが気になっていました。そんな中、クラス分けでTクラスになり、Sクラスの算数の方が楽しかったと不満を口にすることがありました。
そこで「親が与えてあげられるものは限られていて、自分の学ぶ場は自分で手に入れるほかないのだ」と言ってきかせました。先生からは「両クラスのボーダー付近だったものの、今後のことを考えると一度クラス落ちを経験しておいた方が良いのでは」というアドバイスもいただき、この機会を今後につながる意識づけとしました。
その後もこの件は息子との間で度々話題になり、自らの学びに対して責任感を持つようになっていったと感じています。
入試をゲームのように捉え、その攻略方法を訓練するためのサービスとして受験塾を位置づける風潮もありますが、シグマTECHはそういったものとは方向性が異なるように感じています。受験はあくまで手段でしかなく、もっと広い意味で「育ててもらった」という感覚があります。
5年生の頃、息子が「シグマTECHが学校だったら良かったのに」と漏らしていたのは、まさにその本質を言い当てていたようにも思えます。
シグマTECHには3年間通えて本当に良かったと感じています。最後まで楽しんで学びを深められたこと、一緒に「知」を楽しめる気の合う仲間ができたことは、かけがえのない財産になるでしょう。仲間たちとは卒業後も連絡を取り続け、時々集まれる企画を考えているようです。長く刺激し合える仲間を得られたことは、受験の合否にも匹敵する大きな恩恵だと思いますし、そのような関係性を育める雰囲気がシグマTECHの特長の一つなのだと感じています。
Dさん
進学先 武蔵
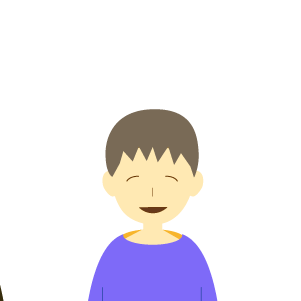
僕は小学3年生の7月ごろからThink!Think!シグマに通い始めました。10月ごろ4年生からシグマTECHに通わないかと親が誘ってきました。よくわからないまま入塾テストを受け、よくわからないまま入塾しました。
4年生は受験などあまりわからず楽しみなが「学び」をやっており良い意味で“塾”という感じがしませんでした。今思うと他塾に比べTECHは授業時間も短く受験を過剰に意識せず受験を楽しめる塾で、僕にはとても合っていたと思います。
僕が受験生だった1年間で、転機が訪れたのは6年生の9月頃で、概ねうまくいっていた1週間があまりうまくいかなくなったことです。
6年生の夏休みまでは課題のステップ1は終わらせており、特別勉強時間が長かった訳でもなく朝テックなどを利用しながら自由時間を確保した上でメリハリをつけて集中して取り組むことで、短時間で課題を終わらせていました。
そして余った時間で自分だけの課題も少しずつ行い、社会の四まとの地理を全部やり直して基本的な知識などの定着を図っていました。そのため模試の成績も比較的安定していました。
ちなみに僕が第一志望校を武蔵中に決めたのは6年の5月ごろです。武蔵中高の文化祭に行った時に、すごく自由と自然がある環境に惹かれ「ここだ!」と思いました。そして家に帰ってきた後、武蔵について調べているうちにさらに惹かれていったため第一志望校にしました。
しかし、6年の夏休みが終わり過去問が始まると、自分が成長できてないのではないかと感じ自信が少しなくなってしまいました。少し減った課題をやって過去問を解いて復習する、ということが一週間で終わり切らないことがおきるようになりました。そして課題を優先してしまうあまり、過去問の復習が1教科分終わっていないまま次に行ってしまうことがありました。
この状況を止めたいと思いながらも止めきれず、10月のサピックスオープンでの成績も低迷していきました。
12月ごろに流石にまずいということで過去問のペースを少し落とし、今まで終わっていなかった過去問の復習を全て終わらせ、怠り気味であった朝テックも友達と朝テック早入り対決をして勉強時間も増やしていくようにしました。結果12月の中旬にあった武蔵模試ではわりとと良い成績を出せました。
しかし少し油断したのか、そのすぐ後にあった志望校ゼミで解いた武蔵の最新の過去問では合格最低点を下回り危機感を感じました。今振り返れば12月ごろの踏ん張りと危機感が大事だったと思います。
1月になり入試が迫ってきていることを実感し、本当に成長しようと思いました。1月は今までの総整理をしながらも得意科目であった算数はあまりいろんなことはせずに、過去問をやる程度にしていましたが、ペースが鈍らないように毎日少しはやっていました。
苦手科目であった国語は過去問をやり青コメを書く、ということを繰り返し行いました。ちなみに1月校は開智所沢の特待Aを受け合格しました。開智系列は同時判定が行われたので、埼玉にある開智系列の学校にも合格しました。1月校の合格は油断に繋げずに自信と希望に繋げました。
1月31日には、国語の個別で教えてもらったポイントや、大量にある青コメをまとめようと今までの青コメから重要な部分を取り出し、紙1ページに似ているものをつなげながらまとめました。また、試験中に意識しやすいよう各学校の国語の試験の時間配分の作戦を確認したり、変更したりしました。
また国語以外の他の教科でも、今までのミスとその対策をまとめて本番でもしないように工夫をしました。おかげで自然と自信がつき入試が楽しみになれました。
ついにたどりついた本番2月1日。緊張したのは前日までで当日は自信(根拠はない)もあってか「やってやるぞ!」と意気込み、高揚していました。ちなみにギリギリの時間に武蔵の試験会場に行ったので約500人の受験生の中で最後に受付をしてしまいました(悔いはない)。
午後の開智日本橋も少し眠気に邪魔されそうになりましたが、問題に集中できたのでよかったです。午後の開智日本橋は得意な算数単科受験を選択したため、1日で5教科しか受けなかったのに思ってたより疲れました。ちなみに試験番号と名前、座席番号を書き忘れたまま試験が終了してしまい、幸い先生が書いてくれましたが、試験番号や名前、座席番号などは試験が始まってからすぐに書くことをお勧めします。
2月2日朝起きたら、開智日本橋に受かっていたことを知らされひとまず安堵。その日はとても寒かったのですが、カイロのおかげで手がかじかまずに桐朋を受けられました。カイロは寒い日には手がかじかむといけないので必須だと思います。
国語では、1月31日に作った1ページまとめに書いた「対比関係を常に意識する」というポイントを意識していたらスラスラ解けてしまいびっくりしてしまいました。午後の広尾ではまたもや約400人の受験生の中で最後に受付をして入室してしまいました(悔いはない)。
休憩時間には友達にも会えてリラックスできました。2月1日は眠気を感じたり疲れを感じたりしたのに、2月2日は疲れや眠気など感じませんでした。
2月2日は前日に比べてさらに楽しむことを意識してリラックスして解いていたため心が軽かったのだと思います。
また2月1日は第1志望の武蔵を受けたため精神的に疲れが出たのだと思いました。精神的な疲れ対策は大事です。
2月3日、今まで一度も合格最低点に届いたことのない海城を受験しました。毎回合格最低点-10点から-35点ほどで危機感を感じていたものの、いつもより3~8問ほど問題を正解すれば良いと考え、いかに凡ミスなどを抑えて問題を解くかしか考えず、怯まず(なぜか自信まであった)受験できました。
1月31日にじっくりと考えた国語の時間配分で実際に解いてみると、今まで試験時間内に全部解き終えたことがなかったのに(毎回記述が2個残っていたり記号問題が5,6個残っていた)、試験時間内に全部解き終わり記述の構成をきれいに書き直し、記号問題を見直す時間まで余りました。改めて時間配分はとても大事で、僕のようなタイムマネジメントが苦手な人はちゃんと考えるべきだと思いました。
2月3日、9:00に武蔵の合格発表が始まりました。海城の受験が終わって合否を見ると、「合格です」と表示され実感はあまり湧きませんでした。でも徐々に嬉しさが込み上げてきました。
過去問を解いたとき合格最低点を取ったことは何回もあったのですが、9月ごろは合格最低点ギリギリだったのが1月の最後のゼミの時には合格最低点+43点で、当日は手応えがありました。9月から2月まで個別指導やゼミなどで国語が足を引っ張っていたのを少し改善できたり、他の教科も成長したりしたおかげだと「半年で成長したなぁ!」と思ったからです。
その後一緒に海城を受験していた友だちと昼ごはんを食べて解散したあと、電車を待ちながら桐朋と広尾の合否を見ました。桐朋は自信があったので受かっていて自信がありましたが受かっていて安堵しました。
広尾は過去問では合格最低点を毎回超えていたものの、合否確認の形が番号を探す形式で倍率の高さを目の当たりにして圧倒されていたため、番号を見つけたときは驚きました(残念ながら特待ではなかったので少し悔しい)。
2月4日学校を休んでのんびりしていたら、仕事に行っていた親から海城の合否発表画面のスクショが送られてきました。合格発表画面には「合格」と書かれていて、広尾の時以上にびっくりしてしまいました。手応えはあったものの、初めて海城②の合格最低点をこえ「1月の終わり頃に解いて合格最低点を下回ってから2月3日までの期間でも、合格最低点を突破するだけの成長をしたんだなぁ! 」と驚きました。周りの環境などにも恵まれたおかげで、憧れであった「受験全勝」を達成することができました。
僕の志望校決めは文化祭60%と説明会40%で決めました。文化祭はその学校の校風などが体感できるので行くことをお勧めします。
また、僕のような国語が苦手科目の人は青コメをたくさん書くことをお勧めします。どれだけ問題を解いても青コメのプロセスをしなければ次に繋がらないので、青コメをとにかく書きましょう! これは算数の問題に関しても量が多くて面倒になった時は、最後のポイントのところだけでもメモして経験を無駄にしないようにしてみてください。弱点が、しらみ潰しのようになくなっていきます。
そして、受験勉強が少しいやになった時は「人生。めんどくさいこともしていいか! 」と思って、気楽に学んでみてください。
それから1月31日など直前の直前は今までの総整理もしてみてください。僕は今までの青コメを全部読んでまとめたりQAを一周したり予シリをパラパラめくったりしていました。
最後にぼくが思う大事なこと5個を箇条書きします。
・自己肯定感は高く自信を持つ。
・自分のこの科目、この単元は誰に負けないぞ!という強みを持つ。
・自分が今本当に成長しているのか考え続ける。
・何でも楽しんでやる。
・メリハリをつけて、やる時はやる遊ぶ時は遊ぶ。混ぜない。
Q.次の条件を満たす自然数を当ててね! 解いたらその数が何を表しているか考えてみてね!
① その数は3桁の数
② その数に19足すと素因数が2のみになる(2の累乗)
③ その数から1引いてできた数は約数が12個ある
④ その数は17の倍数ではない